第1話 とある冬、ラブライブ関西地区予選
「さあ大盛り上がりの関西地区予選も、残すは一位の発表のみとなりました!」
レポーターのお姉さんが張り上げた声が、大阪城ホールに響き渡る。
時は十二月半ば。大阪の街がクリスマスの色に染まる季節。
近畿各府県の予備予選を勝ち抜いてきたスクールアイドルたちが一堂に会し、全力のパフォーマンスを披露した――
その時間は既に終わり、今は非情な結果が下される場面だった。
(まだや……まだ可能性はある……)
ステージ上で多くのスクールアイドルが固唾を飲む中、
背後のスクリーンには、既に発表された二位から四位のグループ名が映っている。
その中に、彼女たち
優勝候補筆頭校の名前はまだ挙がっていない。
つまりはこの時点で、もう地区予選突破が絶望的なことは立火も頭では分かっていた。
それでも奇跡にすがりたい。先輩たちにとっては最後のラブライブなのだ。
何かの間違いでもいい、自分たちの名前が呼ばれてくれないかと――
「栄えある一位は……」
お姉さんの眼鏡にライトが反射し、立火は思わず息を止めて……
そして最後の宣告が下される。
「湖国長浜高校『LakePrincess』!
これで夏に続いての連覇となります! おめでとうございまーす!」
ホールにこだまする歓声と拍手、それにかき消される落胆。
こうして、今年度のWestaの挑戦は終わりを告げた。
最終的にスクリーンに映し出された順位は13位。
参加した28校の、ほぼ真ん中。勝ち進める四枠どころか、十位以内にも入れなかった。
「うわぁぁぁ~~ん! 何でやぁ~~!」
帰宅する客でごった返すロビーの片隅。集まったメンバーの中で、立火の親友が人目もはばからず大泣きしている。
彼女が泣き出したせいで、立火は涙を流すタイミングを失ってしまった。
さりとて彼女を慰める気力もなく、代わりに部長の泉が苦笑して声をかける。
「桜夜、いつまで泣いとんねん」
「だってぇ……グスッ……先輩たち、あんなに頑張ってはったのに……」
「頑張ったのはみんな一緒やろ。ここまでよく付いてきてくれた」
「うぅ……」
「特に小都子は、一年生なのに負担かけてすまんかったな」
「い、いえっ……私は、そんな……」
もう一人の一年生、マネージャーの
そして泉は長いポニーテールを揺らし、明るく声を張り上げた。
「私たちは精一杯やった、悔いはない! せやろみんな!」
その言葉に、他の三年生たちもようやく生気を取り戻す。
せやな、お疲れ様、そういった声が交差する。
ああ、これでもう完全に、この人たちのラブライブは終わってしまうんだ。
その現実に何も言えずにいる立火の頭上に、力のある声が響いた。

「立火!」
「は、はい!」
顔を上げると同時に、泉の両手が立火の肩に置かれる。
「次の部長はお前や。私たちが果たせなかった夢、お前に託したで!」
「……はい!」
そうだ。
これで終わりだからこそ、情けない姿は見せられない。
潔く結果を受け止め、次に繋げるのが後輩の役目だ。
立火は無理矢理に笑顔を作り、どんと自分の胸を叩いた。
「任せといてください! 必ずや私たちの代で、全国へ行ってみせます!」
「おっ、立火ちゃん。大きく出たやないの」
「その約束、忘れたら承知せえへんからな!」
五人の三年生たちが次々と立火の肩や頭に手を置く。
重い約束をしてしまった。
それでも何とか、明るい雰囲気で終わりにできた。
これが新部長の初めての仕事。その先に続く長い道への、最初の一歩だった。
* * *
ホールを出た後、上級生は連れだって大阪の街へと消えていった。
三年間の苦楽を共にした仲間だ。色々と語ることもあるのだろう。
同学年の桜夜、後輩の小都子と晴も家へ帰り、久しぶりの休息を取っているはずだ。
しかし立火だけは、ひとり石垣に寄りかかって、夕暮れに染まる大阪城をぼんやりと眺めていた。
(何が足らんかったんやろ……)
今のラブライブにおいて、関西地区は屈指の激戦区だ。
東京と関東が別地区であることを考えると、全国一と言ってもいい。
とはいえその分、他より一つ多い上位四枠に全国大会への切符が許されている。激戦区であることを言い訳にはできない。
(さすがに優勝できるとまでは思ってへんかったけど、13位はないやろ。いくら何でも低すぎとちゃうか)
(……けどまあ、一つ二つ順位が違ったところで、ここで終わることに変わりはないか……)
思考はぐるぐると駆け巡り、それでも現実は変わらない。
せめて次に繋がるヒントだけでも得て帰りたいと、かつて豊臣が滅びたこの地に留まっていたのだが――
何らかの答えを手にする前に、唐突に前方から声をかけられた。
「おやおや~? 負け犬さんが、一丁前にブルーになってらっしゃる」
反応して顔を上げると、一人の女生徒がニヤニヤと笑いながら近づいてくる。
「戎屋……!」
難波大学附属高校『Number
先ほどの関西地区予選では三位。アキバドームの舞台を手にした四校のうちの一つである。
ライバル校で同学年とあって、立火とは既に顔なじみだ。
ウマの合わない相手として、ではあるが。
「何やねん、人がどこで黄昏れてようが勝手やろ」
「いやあ、お暇な人は羨ましいわあ。私らは全国やからな、忙しくてかなわんで」
「せやったら私に構ってへんでとっとと行けや、この暇人が!」
「おお怖い。負けたからって八つ当たりはやめてーな」
この性格の悪い女は、会う度にこうやって煽ってくる。
売られたケンカは買ってやろうかと、歩を進めようとした時だった。
「駄目ですよ戎屋さん」
「!」
もう一人、声と共に少女が近づいてくる。
「スクールアイドルは常に、他校へのリスペクトを持たなあきません」
「何や、小白川はんも残ってたんか」
白いコートに身を包んだ、長い髪の清楚な少女だ。
天王寺福音学院『
その落ち着いた表情が、今の立火には少々気に障る。
彼女たちの順位は八位。立火たちより上とはいえ、予選落ちに変わりはないのだ。
「ずいぶんと平気そうな顔やな。そっちも負けたっちゅうのに」
つい憎まれ口を叩いてしまうが、和音は平然と受け流す。
「私たち聖莉守に勝ち負けは問題ではありません。自分たちらしいライブができればええんです」
「けっ、相変わらずいい子ちゃん過ぎて腹立つわ」
「ホンマホンマ」
「何で意気投合してるんですか……」
「まあそれはともかく」
ぐるりと二人を見渡した鏡香が、ぴっと人差し指を立てる。
「私ら三人が、大阪市三強の次期部長ってことやな」
「そうなりますね」
「せやな」
三人の間に見えない火花が散る。
そう、いつまでも結果を引きずっている場合ではない。次の戦いはもう始まっているのだ。
春にはこの場の全員が三年生になり、そしてそれが最後の年となる。
次は勝つからな!と立火が宣言しようとしたところで、先手を打つように鏡香の口が動く。
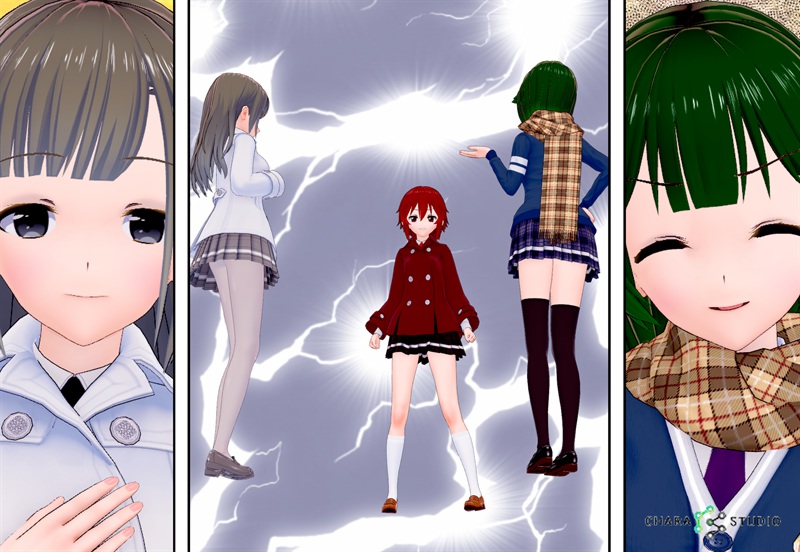
「もっとも? Westaさんはまたここに来れるか怪しいけど」
「なっ! ど、どういう意味やねん!」
「説明せな分からんのか?」
元々上がっていた鏡香の唇の端が、さらにねじ上げられた。
「アンタらは演者の八人中五人が三年生! 卒業した後は三人しか残らへんやないの。そこから上位狙えるほどラブライブは甘ないで」
「そ、そんなんやってみな分からんやろ!」
「そうですよ戎屋さん、失礼です」
たしなめた和音が、ミッションスクールの生徒らしく聖母のように微笑む。
「たとえ予備予選で負けても、精一杯やれたらそれでええやないですか」
「何で負けるの前提やねん! お前が一番失礼やで!!」
「まあ……そんなつもりやなかったんですけど、気に障ったらすみません」
「はあ、もうええわ……」
何だか疲れた。真冬に長時間立っていたせいで、体もすっかり冷えている。
これ以上ここにいても、得るものはなさそうだった。
「私はもう行くわ」
「そうですか。よいクリスマスを」
「はいはい。あと戎屋は私らの代表として東京行くんやからな、恥ずかしいライブ見せるんやないで!」
「はっ、誰にもの言うてんねん」
それ以上の会話はなく、立火は駅へ向かって歩き出した。
夏のラブライブは関西地区予選敗退。
冬のラブライブも関西地区予選敗退。
アキバドームへの道はあまりに遠い。
『必ずや私たちの代で、全国へ行ってみせます!』
(軽々しくあんな約束して、ホンマに大丈夫やったんやろか)
浮かんでくる弱気を、頭を振って追い払う。
一度口に出した以上は、今さら取り消せはしないのだ。
* * *
翌年の三月。
まだ肌寒い空気の中、三年生たちは笑顔で卒業していった。
「うわあああん、先輩がいなくなったぁ~!」
「まーた泣いてるんか桜夜、ええ加減にしときや」
「だってぇ~!」
校門で卒業生を見送ってから、在校生の四人はそのまま視聴覚室へ来ていた。
大阪市の西南、住之江区に位置する住之江女子高校。
そのさらに西端にあるこの部屋が、放課後はスクールアイドル部の部室となっている。
何も映っていないスクリーンに、整然と並べられた長机。
一クラスが入る広さの部屋に、今はたったの四人だけだ。
予選後の三年生は受験に必死で、ほぼ部室には来なかったとはいえ、完全に卒業してしまった今では一層寂しく感じられた。
「ほら桜夜先輩、ティッシュ使ってください」
「ううっ。小都子はいつも優しいなあ」
「感傷に浸るのはそれくらいにして、現実的な話をしましょうか」
二年生二人と一年生二人が向かい合って座る中、マネージャーの晴が冷静に話を始める。
「主力やった三年生が卒業して、我々の戦力は大幅にダウンしています」
「せやなあ。地区予選の後に、戎屋にも同じこと言われたわ」
「難大付属のあいつ? 私あいつ嫌ーい」
「私も嫌いやで。おもろくもないのにニヤニヤ笑いよってホンマに」
「続けてええですか? 何より今のWestaには、作曲者がいません」
「それやな……」
困り顔で立火は腕組みする。
「芸術方面は菊間先輩に任せっきりやったもんなあ」
ラブライブに出場するには、未発表のオリジナル曲が必要になる。
フリー音源を使うとか、音楽の先生に頼むといった手はあるが、どうしても印象は良くない。生徒たちが頑張って一から作り上げる、それがスクールアイドルの美意識であるからだ。
「晴ちゃん、私たちはどうしたらええの?」
不安そうな小都子に、晴は事もなげに言い切る。
「そんなん決まってるやろ。有望な新人を入れることや」
「おっ、やっぱりそれやな!」
立火は我が意を得たりと手を打つが、隣の桜夜は心配顔だ。
「作曲できる子なんて都合よく見つかるんかなあ」
「まあ見とき。今のタイガースのフロントより、私の方が優秀やからな」
「飲み屋のおっさんみたいなこと言わないでくださいよ」
軽口を叩き合ってから、最終的な結論を確認する。
「作曲者を含め、最低五人は欲しいですね。それで元の人数に回復できるので」
「よし、まずはそれが目標やな」
目指す先が定まったところで、四人だけでその日の練習が始まる。
まずは入学式の勧誘ライブだ。
昨年、一昨年に自分たちが迎えられた曲で、新入生を迎えるべく準備する。
何だかんだで大阪市予備予選では三位、関西地区予選でも中堅の順位を得ている。
きっと入部希望者も殺到して、すぐに賑やかな部室になるはず。
その時の立火は、そう信じて疑わなかったのだ。
<第1話・終>