第29話 決戦
「てことで、武器の専門家である新体操部長を連れてきたで」
「武器ってなんや、
週明けの部室にて。
ミーティング中の9名+1の前には、先週食べきれなかったパウンドケーキが並んでいる。
立火の紹介を受けた景子に、姫水はぺこりと頭を下げた。
「福家先輩、受験で大変なときに申し訳ありません」
「いやいや! 姫水ちゃんのためやったらお安い御用やで。
この大一番でセンターとは、応援してきたかいがあったなあ」
「ご声援に応えられるよう頑張りますね」
「それに引きかえ彩谷ちゃん……ほんまに大丈夫? 一、二段落ちるって感じやけど」
「だ、大丈夫ですって! あたしはやる時はやる女っす!」
「まあ、姫水ちゃんに惚れる気持ちはよーく分かるで。一目会ったその時からとはねえ」
「ううう……友達にも散々からかわれましたよ……」
この二人が次のセンターであることは、既にWestaのサイトで発表された。
ついでに晴が筆を振るって、つかさにとって姫水がいかに運命の相手か、愛憎渦巻くストーリーに仕立て上げた。
その先輩につかさの恨みがましい視線が向く。
「別に事前に公表しなくても、当日のサプライズで良かったんじゃないですかね」
「悪い意味でのサプライズにしかならへんやろ。
決戦でいきなりお前がセンターで出たら、ずっと応援してくれてたファンはどう思う。
『ラブライブ舐めとんのか』って思われるだけやで」
「くそう……それがあたしの立ち位置かあ……」
「そうならないよう、お前の姫水への想いはせいぜい物語として消費させてもらう」
「あーもう分かりましたよ! 好きなだけ使ってください!」
「あの、そろそろ本題の方に」
夕理に促されて、景子がそうやそうやと結論を言った。
「手具を使うとしたら、はっきり言ってバトン一択やで」
「え、リボンとかはあかんの? あれ可愛いのに」
ケーキをもぐもぐしながら言う桜夜に、こいつ最後までアホやな、という景子の目が向く。
「あんな激しい動きをするライブで、リボンなんて絶対からまるやろ。
棍棒は危ないし、フラフープもスペース的に無理。ボールで殴り合うわけにもいかへん」
「せやけどバトンとなると……」と立火。
「そう、新体操部では扱ってへん。チア部の道具やな」
この学校にチア部はない。使うとすれば独学で練習せねばならない。
せっかくのヴィクトリアの助言だが、やはり無理か……と諦めの空気が漂ったとき、晴が声を上げた。
「五年前まではチア部もあったので、どこかにバトンが残っているかもしれません。用具室を探してみます」
「そうやな、まだ焦る時間とちゃう。色々試すべきや。頼むで晴」
部長とうなずき合って立ち上がる晴に、景子も残ったケーキを口に押し込んだ。
「バトン探す程度なら私も手伝うで。橘ちゃん、ケーキごちそうさま」
「お粗末様でした」
「福家先輩、何から何まですみません」
「なーに、私は姫水ちゃんの古参ファンやからね。
スクールアイドルもええけど、できれば女優の姿もまた見せてや」
「……はい、できることなら」
二人が廊下に出ていくと同時に、夕理は花歩を部室の隅に連れていく。
「私たちは曲の手直しや」
「そうやね。新しいタイトルも考えないと!」
そして勇魚は、教壇を探って指示棒と定規を取り出した。
「姫ちゃんつーちゃん! とりあえずこれで試したらどうやろ!」
「さすがは勇魚ちゃん、天才ね。彩谷さん、異存はないわね」
「ほんま勇魚に甘過ぎやろ……別にいいけど!」
「面白そうやないか。新センターの実力、まずは見せてもらうで」
立火の指示でスペースを作り、それぞれ武器を持った二人が相対する。
(あたし、こいつに好きって言ったんやな……)
あの日は帰宅してから、恥ずかしさでしばらく悶絶していた。
しかしセンターを譲ってもらえたのは、三年生より決闘に向いているという理由からだ。
馴れ合いも甘さも今は不要。最後までライバル心を持って、戦い抜かねばならない。
流れ出す音楽の中、つかさは定規を振りかざして練習を開始した。
「覚悟や、姫水!」
* * *
「私、ほんまは参謀ちゃんのこと嫌いやってんけどな。冷血そうやし」
「そう、ではなく実際冷血ですよ」
体育用具室をあさりながら、冷ややかに言う晴に景子は笑う。
この子が発案した姫水争奪戦。新体操部が勝っていたら、この一年はどうなっていたのだろう。
でもWestaがここまで来られたことを思えば、これで良かったのだろう。
「まあ、立火は最後までアンタに感謝してるみたいやからな」
「そうですか」
「……なあ、私が口出しするのもおかしいんやけど。
立火が覚悟してセンターを譲ったのも分かるんやけど。
でもできれば、最後かもしれないステージ、立火にも見せ場を……」
「そこはご心配ありません」
開いた箱の中身はリレー用のバトンで、バトン違い。
箱を閉めながら、晴は淡々と言った。
「というか、そうせざるを得ません。
つかさだけではやはり力不足ですから。
立火先輩と桜夜先輩にも、かなりのフォローを頼むしかないでしょう」
「あ、そ、そう? いやー、私いらんこと言うたわー!」
照れくさそうに頭をかく景子に、晴はほんのわずかだけ微笑んだ。
「福家先輩の心遣い、部長には内緒にしておきますよ」
「そうしておいて……あ、これバトンとちゃう?」
晴が部室に戻ってくると、つかさが床に膝をついていた。
それを見下す形で、姫水が指示棒を突き付けている。
「どうしたの彩谷さん、その程度?」
「ま、まだまだっ……」
「センターを引き受けた以上は覚悟してもらうわよ。
何としても当日までに、全国に行けるだけの力を身に着けてもらう。
辞退したくなったらいつでも言いなさい!」
「うっさいわ! もう一度!」
「動きが遅い! そこはもっと凛々しく!」
容赦のない矢継ぎ早の指示に、桜夜と小都子は震えあがっている。
「姫水、とんでもない鬼コーチやで……」
「私たちを指導してたときは、相当手加減してたんやねえ……」
「おっ、晴。どうやった?」
立火の声に、夕理と花歩も作業を中断して近寄ってきた。
部員たちの前の机に、晴の手が戦利品を並べる。
「六本だけ見つかりました」
「いかにもバトンって形ですね!」
「勇魚の感想は意味不明やけど。
しかしこれを手にしたからには、ある程度のトワリングは期待されるやろな」
確かに、単なる棒切れとして持ってるだけでは失望されるだろう。
かといって素人の自分たちが、歌って踊りながらバトントワリングなんてできるのだろうか。
「で、同じ場所にこういうものもあった」
晴が出したのは何かの留め具である。
短い革バンドふたつが、小さい部品で繋げられている。
「晴ちゃん、これは何なん?」
「ちょっと小都子の人差し指に付けてみてくれ」
「こう? ……あー、なるほど!」
指とバトンを結ぶと、部品が回るようになっていた。
特に練習せずともバトンは勢いよく回転し、一年生たちから歓声が上がる。
「これならうちでも何とかなりそうです!」
「でもこれで繋いじゃうと、あの技は無理ですよね。高く投げるやつ」
「エーリアルな。そのへんは別途考えるとして」
花歩に答えてから、晴は改めて立火へと向く。
「決断をお願いします。使いますか? バトン」
「使おう!」
もはやいちいち迷わず、立火はその場で即断した。
「安全策で全国行ける状況とちゃうんや。こっから先はバクチに次ぐバクチやで!」
「言い方を考えてください……『一か八かの勝負』とか」
「夕ちゃん、あんまり変わってへんで!」
残り二本は晴のつてで他校から借りることとした。
作業に戻った曲作りコンビを除き、六本のバトンが回転を始める。
ブラッシュアップだけで済むと思ってたのに、かなり忙しい練習が必要になった。
だが、より楽しくなったというものだ!
一時間後、夕理は机に突っ伏していた。
「あまり改善の余地がなかった……」
「まあまあ、先週の時点でだいぶ完成してたってことで。
歌詞もそこまで変えられへんなー。大阪弁は減らしたけど……」
「……でもセンターが別人で、バトンも加わるんや。使い回し感はだいぶ消えると思う」
「そやね。あ、曲のタイトルも変えないと」
腕組みして悩み始める花歩に、夕理が不思議そうに尋ねる。
「そもそも決闘がテーマなのに、何でbattleにしたんや。duelとちゃうの」
「デュエルはカードゲームみたいやって部長が」
「え! そんなん言うたっけ」
練習中の立火が、耳に届いた声に慌てて振り返った。
「たぶん雑談で適当に言うただけやで。気にしないで使うてや」
「そ、そうですか。でも単純に使うのは、ありきたりな気がするなあ……」
バトンの代わりに鉛筆を回しながら、皆の練習風景を眺める。
つかさと姫水が、バトンを剣のようにして切り結んでいる。
残り少ない時間。重責を負った二人には、この一瞬一瞬が決闘なのだ。
「Dueling……」
「え、現在進行形?」
思わず呆れ声の夕理だが、花歩は立ち上がって二人のセンターに駆け寄った。
「『Dueling Girls!』」
「な、何や突然? あ、新しい曲名か」
「うん! 二人はどう思う?」
「いいんじゃないかな。『バトル・オブ・オオサカ』より広く受け入れられる感じで」
姫水の言葉に他の部員たちも賛同し、完成した曲に決意を込めた。
決戦が終わるまで、皆でDuelingしていくことを。
だがこのとき、既に桜夜は限界だったのだ。
* * *
「では帰りのミーティングを……」
「乙女心が足りてへん!」
今日の活動を締めようというところで、いきなり桜夜がわめき出した。
「最近バトルとかデュエルとかそんなんばっかやんけ!」
「す、すみません……」
「あ、いや、花歩が悪いんとちゃうで!?
それがテーマやからしゃあないけど、もっと可愛らしいこともしたい!」
「先週パンダに和んだやろ」
「部活の中でしたいの!」
わがままを全開にした桜夜は、人差し指を立てて重々しく言った。
「というわけで、みんなで壁ドンをやろう」
「またアホがアホなことを……」
「ね~、いいやろ~? どうせこの先ひたすら練習なんやから、今日だけ~」
「もう、仕方のない先輩ですねえ。是非お二人でやってください!」
「小都子!?」
なぜか小都子がうきうき顔である。
立火と桜夜の壁ドン。後輩としてここまで心惹かれるものがあるだろうか。
外堀を埋めるべく、晴へと話を振った。
「晴ちゃんもブログのネタになってええやろ?」
「確かに。ここらであざといファンサービスも入れたい」
「うーん、部のためになるならまあ……。
あ、一年生は帰ってええで。こんなん付き合わなくても」
「いえいえ! こんな面白そうなの、見逃すわけないやないですか」
「正直下らないと思いますが、私はつかさと帰りたいので……」
弁天組はそう答え、長居組も帰らない。
勇魚もさすがに壁ドン程度では赤くはならず、楽しそうに見守っている。
花歩は少し複雑だが、あわよくば自分も部長に壁ドンを……という下心で残った。
立火は仕方なく立ち上がり、小さい溜息とともに近づいていく。
期待に満ちた顔で、壁に張り付いた桜夜へと。
「あー、これで壁に手をついたらええの?」
「あとは何かドキドキする台詞を言うんやで!」
「勇魚、そっちから撮影しろ」
「はいっ!」
晴と勇魚がカメラを構えたその先で……
立火は壁をドンすると、精一杯胸が震える台詞を言った。

「おうワレ、返済期限はとっくに過ぎとんのやで」
「別の意味でドキドキするわ!!!」
夜の部室に桜夜の抗議が響き渡る。
目を逸らして口笛を吹く立火の、その胸ぐらを掴んで問い詰めた。
「何でヤクザなん!? ねえ何で!?」
「人を壁際に追い詰めるって、普通に考えてヤーさんの所業やろ?」
「乙女心のカケラもない!!」
そのとき、離れて見ていた夕理がつかつかと近づいてきた。
怒りの表情で、立火にびしりと指を突き付ける。
「ヤクザを笑いのネタにしないでください!」
(そっち!?)
「奴らは撲滅すべき反社会勢力ですよ! ギャグで済むと思ってるんですか!」
「いやほら、新喜劇のヤクザと現実のヤクザは別物やから……」
「社会に誤ったメッセージを与えます!!」
(は、話がどんどん乙女心から離れていく……)
しょせん立火に少女漫画展開を期待した自分がアホだった。
そう思い直した桜夜は、期待できそうな後輩を指名する。
「次、つかさ! ギャルっぽいくせに一番乙女な子!」
「そーゆー表現やめてくださいよ! んー、なら相手は花歩で」
「私!? 何でやねん!」
「一番反応が面白そうやから」
当てが外れた花歩だが、断れる空気ではない。
仕方なく壁を背にし、近寄ってくる相手に小声で文句を言う。
「もー、何で姫水ちゃんを選ばへんの」
「(アホか、あたしの心臓が破裂するわ!) ええやん、花歩ってあたしのこと好きやろ?」
「くそう、余裕ぶった態度がムカつく……」
まあ実際好きなのだけど……。
つかさの右手はスマートに、花歩の左耳に風を当てて壁をドンした。
「花歩……」
「つかさちゃん……」
憧れの女の子が目と鼻の先で、自分だけを見つめてくれている。
こういうのも悪くないかも……と花歩が浸り始めていると。
つかさの口が、にやあと悪く歪んだ。
「部長さんが見てる前でこういう事するのって、めっちゃ背徳感ある」
「う……うぎゃーー! みみ見ないでください部長ーー!」
そう言われても、という顔の立火の前で、花歩はじたばたと逃げようとする。
が、つかさの左手は獲物のあごをクイッとして、ニヤニヤと詰め寄った。
「くっくっくっ、そう言いながら感じてるんやろ? 花歩はいやらしい子やなあ……!」
「い、いやっ……見ないで部長っ……!」
「何やコレ」

完全に呆れ切った立火がそう呟いた時。
夕理が急に立ち上がると、とぼとぼと扉の方へと歩いていく。
「少し廊下で頭を冷やしてきます……」
「ゆ、夕理ちゃん!」
「一人にしてください……」
小都子は後を追おうにも、自分も大盛り上がりだっただけにばつが悪い。
つかさも花歩を解放すると、苦笑しながら頭をかいた。
「うーん、ちょっと夕理には刺激が強すぎたか」
「もう! 明日のお昼、私と夕理ちゃんめっちゃ気まずいやろ!?」
「興奮してたくせに何言うてんねん」
「うがーー!!」
「んー、なかなか面白かったけど、ちょっとつかさは調子に乗りすぎやな」
腕組みしたツインテール先輩は、続けて逆転の一手を指示した。
「次、姫水! つかさが動揺するとこ見せたって!」
「はあ……」
「んなあああああ!?」
打って変わってヘタレるつかさに、花歩は因果応報! と親指を立てている。
つかさも本心では、姫水にしてもらいたい気持ちはあるのだけれど。
それを気取られまいと、むきになって抗議した。
「ななななんであたしが姫水と!」
「既に動揺してるようですし、やらなくても良いんじゃないですか?」
「はあ!? だだ誰が動揺してるっちゅーねん! ええで、受けて立とうやないか!」
(彩谷さんって本当に面倒くさいわね……)
仕方なく姫水が一歩踏み出すだけで、つかさは後ずさりして壁に追いつめられる。
スマホで撮影している勇魚が注文を付けた。
「姫ちゃん、もうちょい笑ってや~」
「勇魚ちゃん、これでいいのよ。壁ドンとは本来シリアスなものよ」
「そういうもんなん?」
(く、くそっ。姫水になんて絶対負けへん! 逆にドキドキさせたるで!)
などと考えながらも既に負けつつあるつかさに、姫水は真剣な顔で一歩一歩近づく。
(この子、私のことが好きなのよね……?)
人から好かれるのは昔からで、もう慣れ切っているはずだった。
けれど嫌われてると思っていた相手から、急に好きと言われればさすがに戸惑う。
つかさが計算してやっているなら実に腹立たしい。
ドン……!
優雅な動きで壁に手をつかれ、つかさは耳まで真っ赤になっている。
その呼吸が届きそうな距離で、姫水の唇は流麗に動いた。
「『つかさ』」
(あ……)
つかさの目が見開かれた。初めて、下の名前で呼ばれた。
夢にまで見た瞬間だったのに……
それがこんな、下らない遊びでだなんて!
(こいつ心底、あたしのことどうでもいいんやな……!)
実感させられて、じわ、と涙が浮いてくる。
困ったような顔で、姫水の指がその水滴をぬぐった。
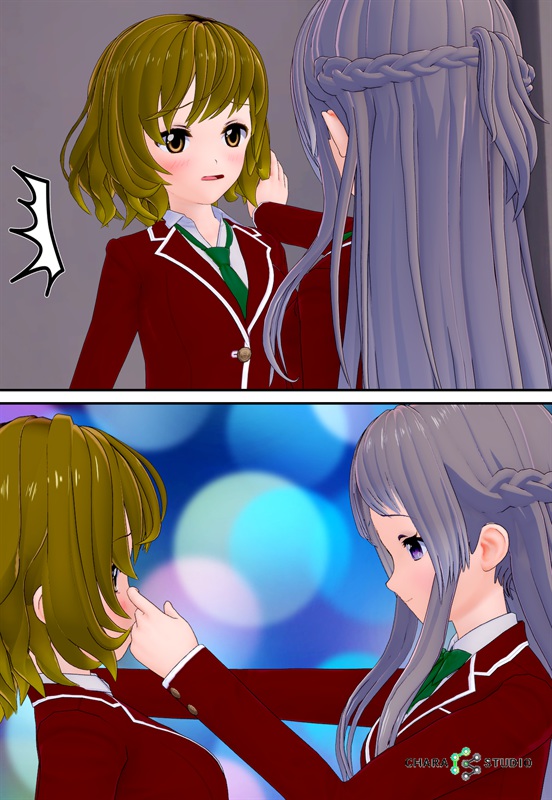
「また泣かせちゃった? ごめんね」
「う……ううう……!」
こいつの前でみっともなく泣くのは、これで何度目だろう。
つかさは必死で姫水を押し返すと、何とか壁際から脱出する。
「あ、アホくさ! 壁ドンとかとっくに流行遅れやっちゅーねん!
こんなん付き合ってられへんわ! アーホアーホ!」
小学生みたいな捨て台詞を残して、そのまま廊下へ逃亡していった。
気まずさが充満する部室の中で、立火は発案者を責め立てる。
「おい! どうしてくれるんや、この空気!」
「あ、あっれぇ~。乙女のロマンのはずが、何でこんなことに……」
「全くもう、本当に桜夜先輩は仕方ないですね」
姫水は呆れ笑いを浮かべつつ、人差し指を立てて断言する。
「こういうことは、まず勇魚ちゃんにしてもらうべきなんです」
* * *
廊下で夕理が深呼吸していると、いきなり戸が開いてつかさが飛び出してきた。
その赤くなった目を見て、中で起きていたことを察する。
「また藤上さん?」
「う……うん……」
手の甲で目をこするつかさを見て、夕理は微笑む。
全てを受け入れた諦観の上で。
「ほんま、人を好きになるって大変やね」
「そう……やね」
二人で声を出さずに笑い合う。
どんなに大変でも、この想いを捨てることも後悔することもないけれど。
と、部室の中からは声のある笑いの音がする。
扉を少し開けて覗いてみると……。
「えいっ、どーん!」
「あはは、ただのタックルやないかーい」
勇魚と立火。最も身長差のある二人の壁ドンは、勇魚の手が届かないため、立火の脇の下を通る形になった。
「立火せんぱーい!」
「おっ、よしよし」
そのまま嬉しそうに、立火の胸へと顔を埋める勇魚。
そして勇魚の頭を撫でる立火に、空気はすっかりほのぼのしている。
一見笑顔ながら、内心で引きつっている花歩を除いて。
(おっ……落ち着くんや私! こんなん微笑ましいワンシーンやないか!)
(姫水ちゃんも楽しそうに笑ってるやろ! 私だけ心の狭いこと言えるわけが)
「いやー、ほんま勇魚は可愛ええなー」
桜夜も満足そうに写真を撮っていて、ますます花歩は何も言えない。
その間に、つかさは何食わぬ顔で夕理と一緒に戻ってきた。
「なんかもう、ほとんど親子っすね」
「おっ、二人ともお帰り。ならこれでお開きで」
「待ってください立火先輩! まだ私がしてもらってません!」
小都子が柄にもなく、強い口調で主張した。
十分堪能させてもらったが、自分だって壁ドンされるチャンスを逃すものか。
もう帰りたい立火が投げやりに進める。
「分かった分かった。相手は誰や」
「うーん。夕理ちゃんと言いたいけど、嫌そうやね」
「当然です。こんなの茶番すぎます」
「なら言い出しっぺの桜夜先輩で」
「え、私がやる側!?」
思わず自分を指さす桜夜の前で、小都子はわくわくしながら壁に背を預けた。
可愛い後輩の頼みは断れず、仕方なく近づく桜夜に、にやついた相方が声をかける。
「さっき私にあれだけ言うたんや。さぞ心ときめかせる台詞を聞かせてくれるんやろなあ」
「うっさいわ! 今考えてるとこ!」
ドン!
(って、しまった!)
加減が分からず、つい強めにドンしてしまった。
けれど目の前の女の子は、先輩を信頼しきって落ち着いている。
(小都子、いつ見ても可愛ええなあ……)
この優しくて先輩思いな子に、何と言ってあげればよいのか……。
考え抜いた桜夜は、きりっとした顔でハイセンスな言葉を吐き出した。
「き……君の瞳は一万ボルト」
「いつの時代のセンスやねん!」
立火と花歩のツッコミが同時に突き刺さる。
部員たちが笑い、桜夜も照れている中で……
同じく笑っていた小都子の表情が、ふと心配そうなものに変わった。
両手を上げて、すぐ近くの桜夜の両頬を包み込む。
「先輩、曲のことだけやないんやないですか」
「え……」
「何か別のことで、ストレスが溜まっていたんでしょう。
それで発散したくて、こんなこと始めたんとちゃいますか?」
「ううう……」
さすが小都子には見抜かれてしまった。
そして桜夜のストレス源なんて、この時期においては決まっている。
壁に手をついた態勢のまま、彼女は暗い顔で白状した。
「じ、実は受験勉強してても、全然頭に入ってこなくて……」
「先輩……」
「昨日も勉強せなあかんのに、つい漫画読んじゃって……」
『それは駄目やろ!』
一年生たちの無言のツッコミを聞きつつ、カメラをしまっていた晴が部長に尋ねる。
「実際どうなんですか。桜夜先輩の受験の見込みは」
「かなり易しい大学やから、いくら桜夜でも真面目にやれば受かると思うんやけどなあ」
「そのハードルが私には高いの!」
壁ドンしたまま言い訳する先輩を、小都子は正面からそっと抱きしめた。

「確か最後の合格発表は、卒業式より後ですよね?」
「う、うん。それより前に決めたいけど……」
「どちらにせよお別れのときは、先輩の泣き顔ではなく、笑顔が見たいなって思います。
私だけでなく、後輩たちはみんなそう思ってますよ」
「小都子……」
桜夜は壁から手を離し、後輩を抱きしめ返す。
既に涙は引っ込んでいた。
「うん……分かった。後輩のためやったら、私はやれるで!」
「その意気です!」
「あ、さっきの台詞、私のスマホに録音してくれる? サボりそうになったらそれ聞くから」
「え、改めて言うのも恥ずかしいですけど……はい、私でよければ」
「先輩先輩! うちにも応援メッセージ入れさせてください!」
「おっ、勇魚の声があれば百人力やで!」
他の一年生もそれに続き、夕理も仕方なさそうに声を吹き込む。
「『またサボってるんですか? 最低ですね。失望させないでください』
これなら精神的に効くと思います」
「効きすぎや! でも、ありがとね」
そんな光景を、立火は微笑みながら温かく見守る。
変な遊びだったが、ハッピーエンドに少しだけ近づいたようだった。
(私の方は卒業式前の発表や)
(卒業式は絶対笑顔で送ってもらうで!)
* * *
帰りの電車の中で、つかさのスマホにメッセージが届いた。
珍しく晴からだ。
『欲しいかと思って』
「なあああ!?」
姫水に壁ドンされ、真っ赤になってる自分の写真だった。
全くあの先輩は! 余計なことを! とか言ってるつかさに、夕理はついツッコんでしまう。
「いらないなら消せば?」
「いや、うん……まあ、せっかく送ってくれたんやからね……」
スマホをしまうつかさに、夕理はくすくす笑いながら思い出していた。
初PVの後で電車が満杯になったとき、つかさが壁ドンの形で守ってくれたことを。
自分には、あの思い出だけで十分だ――。