第6話 あなたに依存しないために
「――以上が、私とつかさの顛末です」
夕理の言葉が終わり、部室内に沈黙が降りる。
部員たちが声を失う中、桜夜だけが内心で毒づいていた。
(アホらし。要は自分が性格悪いからハブられて、つかさって子が巻き込まれただけやろ。長々と聞いて損したわ)
「その中一の時にハブった奴ら、酷い連中やな! 人情の町大阪の名が泣くで!」
「ええー!?」
「ん、なんや桜夜」
「別にイジメられてたわけとちゃうやろ!? 話にも出てきたけど、誰でも友達選ぶ権利はあるやろ!」
「何やねん、冷たいやっちゃなあ」
「私が悪いの!?」
「お、お二人とも。そこは本題ではないのでそのへんで」
三年生たちをなだめてから、小都子は改めて夕理に向き直る。
この子にとってつかさが全てな理由は、分かりすぎるほど分かった。
だがこの後、どうしたらいいのだろう。
どうしたら二人は、問題なく一緒にいられるのだろうか。
自分が話せと言ったくせに、結局何も思いつかず。小都子は不甲斐なさを噛みしめながら、参謀に丸投げするしかなかった。
「あの……晴ちゃん」
「うん」
考え込んでいた晴が、すっと夕理の髪を指さす。
「今つけてるリボンが、さっき話に出たそれやな」
「最初のは毎日つけててヨレヨレになったので……見かねたつかさが去年新しいのを買ってくれて、これは二代目です……」
「うわキモッ」
桜夜の率直な感想に対し、場の全員から非難の視線が集中する。
涙目になった桜夜は部屋の隅へ行って、いじいじと床に指で文字を書き始めた。
「ええねんええねん。そうやって私を悪者にしとったらええんや……」
「あの人は放っておくとして、花歩、仕事を頼みたい」
「私ですか!? 分かりました、何でもします!」
すっかり蚊帳の外だった花歩が、話を振られて俄然張り切った。
わくわくしている彼女に、晴が淡々と作戦内容を伝える。
「今日……はもう遅いから明日でええか。部費からお金出すから、難波あたりに行ってリボン買うてきて」
「? はい」
「で、それを夕理にプレゼントすると」
「は、はあ」
「夕理はそれをつけて、彩谷からもらった方はゴミ箱に捨てる。上書きっちゅうわけやな」
「晴ちゃんちょっとえげつなくない!?」
小都子の叫び声が部室内に響き渡った。
三年生もさすがにドン引きし、そして事態を理解した夕理は、すがるように頭部のリボンを押さえたまま、涙目でカタカタ震えている。
「彩谷の精神的庇護から脱するには、これくらいは必要やろ」
「なんか悪意を感じるんやけど!?」
「そんな事はないで。私、誰かに依存してる奴って大っ嫌いやけど、そんな私情は一切交えてへんで」
「ホンマにぃ~!?」
「ホンマホンマ」
小都子から近くでまじまじと見られても、晴はしれっとしたものである。
何とかして震えを止めた夕理が、うめくように言う。
「……いえ、やります。私が真人間になるには、確かにそれくらいしないと駄目なんです」
そして弱々しい顔を同じ一年生に向ける。こんな生気のない子が、この前プンスカ怒っていた彼女と同一人物なんて。そう戸惑う花歩に夕理は頭を下げる。
「変なこと頼んでごめん。協力してくれる?」
「う、うん。私は平気やけど……」
他の面々も困ったように顔を見合わせるが、他に名案があるわけでもない。
結局微妙な空気のまま、軽く練習してその日は解散となった。
* * *
「夕理ちゃん」
重い足取りで昇降口に向かう夕理を、呼び止める声がする。
よろよろと振り向くと、追いかけてきたのは小都子だった。
「ほんまに大丈夫? 無理せえへんでもええんよ。部員増やしたいなんて、私たちの勝手な都合なんやから」
「いえ、お気遣いなく……私こそ、勝手な欲求のためにやっていることなので」
つかさと一緒に部活をしたい。
そのために、つかさへの重すぎる気持ちを減らさなければならない。
言葉にするとあまりに馬鹿馬鹿しい。
そもそも、この欲求は本当に満たそうとして良いものなのだろうか。
それこそ依存している証拠ではないのだろうか。
そんな夕理の内心を知ることもできず、小都子はまだ少し逡巡していたが……
「うん……そうやね」
吹っ切ったように、少し遠くへ視線を向けた。
「欲しいものがあるなら、そのためにちゃんと戦わないとね」
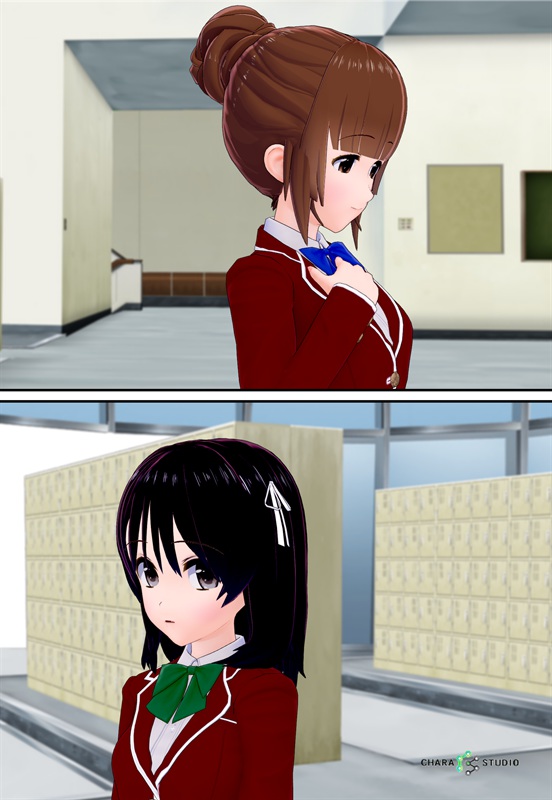
夕理は思わず顔を上げる。
今までどこかぼんやりしていた小都子の姿が、急にクリアになって夕理の目に映った。
それくらい、意外な相手から意外なことを言われた。
「……先輩は、欲しいもののために戦ったことがあるんですか」
「ここに入学するとき、親と少しね。まあ、よくある話や」
「そう……なんですか」
失礼ながら、地味で影の薄い先輩だと思っていた。
まだ知り合ったばかりだけれど、優しくて温和なだけの人だと。
そんな彼女でも戦ったことがあるのだという。
それなら――
自分にも、意志さえあれば戦えるのかもしれないと思った。
* * *
「花ちゃん、一緒に帰ろー……ってなんか疲れた顔やな」
「ちょっと色々あってね……」
「うち、花ちゃんのライブ楽しみなんやけど!」
「うーん、当分無理かも。ボランティア部はどう?」
「なんかお菓子食べてお喋りしてるだけやったから、うち一人でゴミ拾いしてきたで!」
「え。だ、大丈夫なの?」
「大丈夫や、みんないい人やもん!」
勇魚は誰に対してもいい人扱いなので、少し心配になる。一年生がそんな突出した行動をして疎まれないのだろうか。
そう考えながら並んでバス停へ向かっていると、後ろから声をかけられた。
「花歩!」
呼び止める声に振り向くと、立火がこちらに走ってくる。
「あ、部長」
「先輩、こんばんは!」
立火が眼前まで来たところで、隣の勇魚が大声で挨拶した。
「こんばんは! 元気な挨拶で結構やな!」
「はいっ、それが取り柄なので! ほな花ちゃん、うちはバス停行ってるな」
「うん、バス来たら先帰っててええよ」
「何を水くさいこと言うてんねん。ちゃんと花ちゃんのこと待ってるで!」
たったっと駆けていく勇魚を見送って、立火は感慨深げに顎を撫でた。
「なかなか気持ちのええ奴やな。我が部に欲しい人材や」
「もうボランティア部に入っちゃってますよ」
「うーん、よその部員に手ぇ出すんはさすがに仁義を欠くか」
諦めた立火はくるりと花歩の方を向いて、本題を切り出した。
「なんかごめんな、あんまりアイドルらしいことさせてやれなくて」
「い、いえ、まずは部員集めるのが先ですから! ただ、まあ……」
花歩の目がふっと暗くなる。
「明るく爽やかな青春が始まると思った矢先に、あんな重くてドロドロの愛憎劇に直面するとは思いませんでしたけど……」
「うん、私も予想外やったわ……」
重苦しい雰囲気が場を覆うが、それを吹き飛ばすように立火が声を上げる。
「けどこの件が済んだらPV撮るから!」
「PVですか!」
「夕理の曲を使えるし、彩谷も入ってくれたらきっと賑やかなPVになるで。花歩のパフォーマンスにも期待してる!」
「は、はいっ! どこまでできるか分かりませんが、頑張ります!」
その後は去年のPVの話などをしながら、分かれ道まで二人きりで歩いた。
すっかり上機嫌でバス停に向かうと、勇魚の小さな姿が待っていてくれた。
「あれ花ちゃん、急に元気になってる」
「えへへ、まあねー」
* * *
今日も一人で食事と入浴を済ませてから、外したリボンを机に置いて、まじまじと見る。
本当にこれを、明日捨ててしまうのだろうか。
迷いを残したまま、重い指でLINEを起動する。
『今、大丈夫?』
つかさもくつろぎ中だったのか、すぐに返事が返ってきた。
『どやった?』
『今日はほとんど昔話だけで終わった』
『色々あったもんね』
『あのね』
一瞬躊躇する。
いい加減しつこいと思われないか。
つかさの配慮を踏みにじっていないか。
逡巡に引っ張られつつも、しかし今さら後には引けない。
『私がつかさに依存しなければ、つかさは入部してくれる?』
返事が来るまでの時間、緊張で胃が痛くなりそうだった。
ようやく返ってきた答えは、怒ってはいないようだが、困惑が感じられた。
『そらまあ、それを理由に断ったんやから、理屈上はそうなるけど』
そして数秒の溜めの後、鈍器のような五文字が送られてくる。
『できるの?』
(――――!)
呼吸が止まりそうになる。
つかさが好き。
三年前から一度たりとも変わらないこの想いを、本当に制御できるのか。
『明日、また連絡する』
結局直接は答えられず、そう打つしかなかった。
* * *
知り合ったばかりの一年生と、地下鉄に揺られている。
隣の彼女は気まずそうな顔で、会話したくても話題がない。
「アクセサリーってどこで探したらええの? 私こういうの疎くて……」
「なんばパークス行った方がええかなあ。普段は買い物とかどうしてるの?」
「つかさが誘ってくれるところに行って、つかさが勧めてくれるものを買うだけ」
「そ、そう……」
「そんな顔せんといて……自分でも言うてて情けなくなる」
大国町で乗り換え、難波駅で降りる。
パークスまで結構歩くのが、今は少し辛い。
つかさが一緒なら、あっという間の距離なのだけれど。
「パークスに到着しました、っと……」
いつ見ても巨大な複合施設の前で、花歩が先輩たちに連絡を入れている。
スクールアイドルをやりたくて入部したのだろうに、こんなことに付き合わせて心底申し訳ないと思う。
かくなる上は、早急に事を済ませるしかない。
客の多いアクセサリーショップで、似たようなアイテムを探した。
「別に同じものでなくてもええと思うけど」
「うん、でもやっぱりそれが、一番夕理ちゃんに似合うてるから」
「あ、ありがと……」
「いつもそれくらい素直ならええのになー」
「う、うるさい」
ようやく見つけたリボンは、形はほぼ同じで、色はバリエーションがあった。
売り切れているのか、白だけが存在しない。
「夕理ちゃんは何色がいい?」
「いや一応プレゼントって体裁やねんから……そっちで決めてほしい」
「そ、そうやんな。うーん……」
原資はWestaの部費である。結局花歩は、赤いリボンを選んだ。
女神ウェスタの火と炎。
これが夕理の背を押す熱になることを願って。
会計を済ませ、近くのベンチに座る。
「そ、それじゃ不肖私めが、リボンを付けさせていただきます」
「う、うん、お願い」
傍から見たら、さぞかし不審者に見えたことだろう。
お互いぎくしゃくしながら、「上書き」の作業に入る。
花歩の手が、夕理の髪に僅かに触れた瞬間――
『ほらほら、似合ってるやろ』
あの時の光景が、愛おしい声が、夕理の脳内に一気に甦った。
『夕理は可愛いんやから――』
* * *
『どうしましょう、泣かれました!』
花歩から送られてきたメッセージに、部員一同暗澹とするしかなかった。
「キモすぎる……」
「桜夜はちょっと黙って……小都子?」
「もうやめてください!」
とうとう小都子が、耐え切れずに両手で机を叩く。
「可哀想やないですか!! あの子は私が引き取って育てます!!」
「なんか錯乱してない?」
「続きが来ましたよ」
冷静な晴の声に、上級生たちはスマホを覗き込む。
『大丈夫だそうです。リボンの交換完了しました』
安堵の息をつくが、いきなりこれでは先が思いやられる。
小都子が勢いよく立ち上がり、鞄から財布を取り出した。
「私、ちょっと行ってきます!」
「おい小都子!?」
部長の声も聞かず、小都子は荒々しく部室を出ていく。
黙って見送る晴の前で、三年生の二人は顔を見合わせる。
一年以上を共に過ごしてきたが、こんな彼女を見るのは初めてだった。